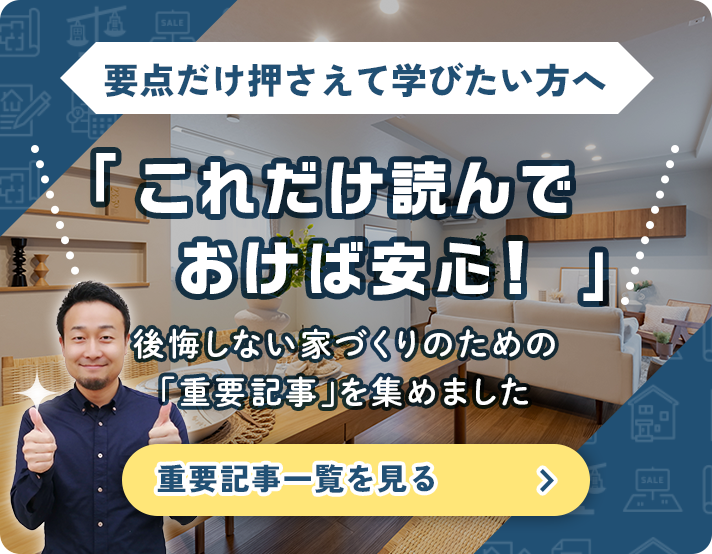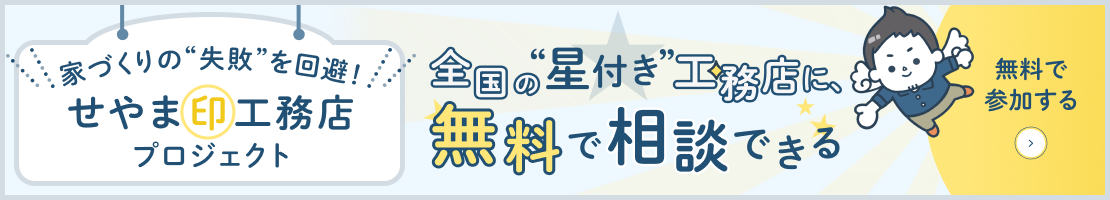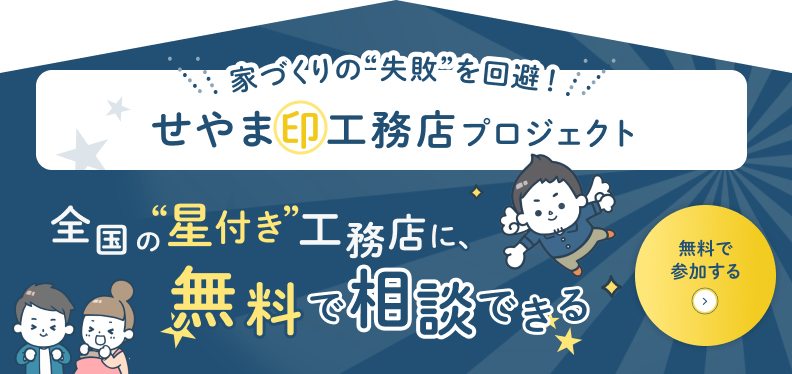2025.09.18
SNSを見て「人とは違う家を建てたい」と思う人も多く、外部の建築家の先生とタッグを組み、家を建てていく仕組みが流行っています。ただし、最近はトラブルが増え、その取り組み自体をやめる工務店も出てきています。というのも、建築家の先生は「おしゃれ」「アート」「人とは違う」というところを優先するため、住んでから「生活動線が悪い」「収納が少ない」「暑い・寒い」という点で後悔する人が多くなっているのが理由です。また、外部の設計士と社内の施工部隊の連携が取れていなくて、工事中にトラブルになるケースもあります。
もちろん「おしゃれな家を建てる」ということ自体は悪いことではありません。ただ、実際に住む家ということを意識し、機能性をしっかり担保した上で、おしゃれな家にしてください。今回は、施主からは見えにくい、住宅会社側から見たリスクを紹介します。これから建築家と家を建てる人だけではなく、おしゃれな家を建てたいと思っている人は参考にしてくださいね。
今回は以下を詳しく解説していきます。
目次
建築家とは?
「建築家」という言葉に定義や資格はありません。ただ、基本的にはおしゃれな家を設計してくれる設計士の先生を建築家と呼びます。ただし、資格が必要なわけではないので「建築家」という言葉に惹かれすぎないようにしてください。
似た言葉に「一級建築士」という言葉もあります。難しい国家資格をクリアする必要があるものですが、これは一般的な家よりも大きなビルやマンションなど、大きな家を建てる時の設計・管理ができるという資格です。一級建築士という言葉を家づくりのPRで使うのは騙しテクニックという側面もあるので注意してください。
建築家は、アーティスティックな作品を作りがちです。ホームページに掲載する際には、次のお客さんの集客に使うために住み心地よりも見栄えの良い家の方が好まれます。ただ、実際に住む施主からすると「ダサい家は嫌だけど、暑かったり寒かったり、収納が少ない、生活動線が悪い家は嫌だ」となりますよね。そのため、まずは機能性を重視してください。
このように建築家や、建築家とタッグを組んだ住宅会社と、施主の考えにはギャップがあることを覚えておいてください。プロの意見を聞くのは大事ですが、少し溝があることを意識しておかないと住みにくい家になるので注意してくださいね。
建築家と建てる家の落とし穴8選
①打ち合わせ回数が少ない
建築家と家を建てる場合は打ち合わせ回数が少なく、3回程度のことが多いです。事前にYouTubeなどでどんな家を建てるか分かっている建築家なら3回で終わることもありますが、何も分からない中で1回目でヒアリング、2回目でファーストプラン、3回目で詰めるとなると結構厳しいです。
建築家のような外部の人と打ち合わせをする場合は、何回打ち合わせができるか確認してください。3回の場合でも、事前にやりとりができないのかを確認するのがおすすめです。細かくヒアリングしてもらったり、建築家の先生の作品を見せてもらってください。その上で考え方が合わない場合、その人に頼まない方が良いです。事前にどんな人なのか、できる限り情報収集をした上で初回の打ち合わせに臨んでくださいね。
②性能を軽視する
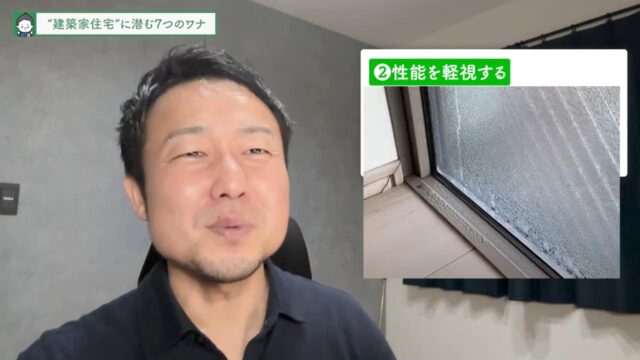 全員ではありませんが、性能面を軽視する人が多いです。平気でアルミ樹脂複合サッシを使って「アルミ樹脂複合サッシを使ってもトリプルガラスにしたら大丈夫です」なんて言う人もいますし、そのような世論を作りにいっている面もあります。一番冷えやすいサッシの部分にアルミを使うのはおすすめしません。少しでも隙間があると空気が入り結露が発生して、内部結露といって木材が腐り、シロアリが来るリスクがあります。
全員ではありませんが、性能面を軽視する人が多いです。平気でアルミ樹脂複合サッシを使って「アルミ樹脂複合サッシを使ってもトリプルガラスにしたら大丈夫です」なんて言う人もいますし、そのような世論を作りにいっている面もあります。一番冷えやすいサッシの部分にアルミを使うのはおすすめしません。少しでも隙間があると空気が入り結露が発生して、内部結露といって木材が腐り、シロアリが来るリスクがあります。
そんなリスクを取ってまでおしゃれにするのはおすすめしません。アルミ樹脂複合サッシではなくオール樹脂サッシを使ってください。それでもLow-eのペアガラスで高さ2,200mmまでのものがありますし、幅2,500mm以上のものもあります。寒冷地に住んでいる人や予算がある人の場合、トリプルガラスの幅2,400mmのものもありますし、FIXガラスでは枠の細いおしゃれな樹脂サッシもあります。このようなものを活用して、機能性とアートを両立してください。住み心地は一番大事なので、窓はアルミ樹脂複合サッシではなくオール樹脂サッシにしてくださいね。
③メンテナンスを考えない
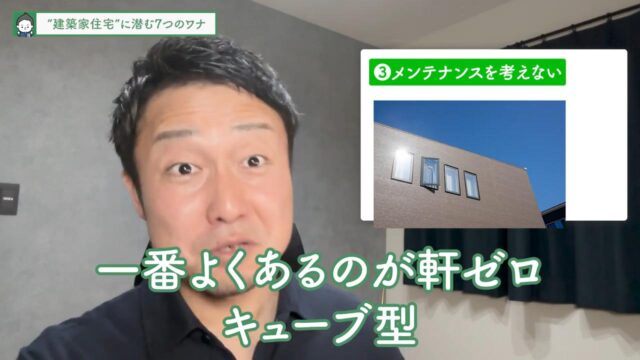
一番よくあるのが、軒ゼロ・キューブ型の家です。軒ゼロにして外壁を濃い家にして窓を小さくすると、確かにデザイン住宅っぽくなります。ただし、雨漏りのリスクが高いですし、日射遮蔽ができないことがあります。それなのに、軒ゼロ・キューブ型の家にする人が多いので気を付けてください。
 板張りにする人も多いので注意が必要です。外に木を張ると1年ごとのメンテナンスが必須です。
板張りにする人も多いので注意が必要です。外に木を張ると1年ごとのメンテナンスが必須です。
木製サッシなども白化してきますよ。メンテナンスできる人なら良いですが、そうじゃない人にはおすすめしません。ただ、木目は格好良いので、木目調の外壁材や軒天を使うのがおすすめです。
④住むと不便な間取り
余裕のある空間があった方が良いですし、廊下を上手く使ったり縁側を作るとおしゃれになります。ただ、予算があるなら良いのですが、映えの要素を充実させるために収納をないがしろにする建築家が多いので注意してください。「収納は全て2階にしましょう」なんて言うので、注意が必要。リビングを優先的に大きくすることは大切ですが、収納の多くが2階だと住みにくいです。
家の優先順位の1位と2位は動線と収納です。おしゃれさよりも、まずはそこを優先する間取りづくりをしてくださいね。
⑤金額が高くなる
「余白や中庭を作りましょう」のように、予算を無視して提案してくる建築家もいます。お金を出すのは施主なので、コストの上限はしっかり抑えてください。その上で「これに収まるなかでベストを尽くしてください」とお願いするのがおすすめ。予算の上限がある中でベストなプランにするのがプロです。予算を伝えて、予算内に収めるように伝えてくださいね。
⑥追加費用の金額を把握していない
標準仕様を変える部分や「これをやったらいくらになりますか?」という質問に対するレスポンスがめちゃくちゃ遅いことがあります。建築家は外部の人なので、社内の価格設定を知らないことがあります。そのため、レスポンスが遅くて待っている間に間取りが決まってしまい、追加オプションの価格が後から分かって大変なことになることも。
外部の建築家に限らず、社内のプランナーの場合でもこういうケースはあります。このような状態になったら営業マンに伝えて「金額が分からない人と打ち合わせをしても困るので、同席してください」などの対策をしてください。
プランの打ち合わせ中に「追加費用の金額がすぐに出てこないのがストレス」と言う施主は多いです。契約する前は分かりにくい点ですが、とにかくすぐに金額が出せる状態にしていくことは、施主側が意識してください。
⑦施工のトラブル
外部の建築家は、社内の施工ルールを知らないことが多いです。そのため、図面上は成り立っていても施工したら収まらないことがあります。また、現場で施工してて収まらない時に、現場監督が社内の設計士に確認し、社内の設計士が建築家に聞く、という伝言ゲームになることがあります。これで連携が取れなくて現場が進まずに工程が遅れることや、無理に収めて仕上げが汚くなることがあります。
建築家と現場監督の連携が直接取れる状態になっているのかを確認してください。家を建てるのは営業マンでもプランナーでもなく、職人です。職人が施工できるプランにしていくことはめちゃくちゃ大事なので、しっかり確認してくださいね。
⑧プライドが高い
建築家はプライドが高い人が多いです。「先生」って呼ばないと機嫌が悪くなったり、いただいた提案に対して質問や注文をしたら文句を言う人もいます。「大きすぎるので小さくしてほしい」と言ったら「一生に一度の家づくりをケチってはいけない」なんて言う人もいます。
普段から「施主側も工務店に配慮することが必要」「お金を出したからと言って無理を言ってはいけない」とお伝えしていますが、やはりお金を出すのは施主なので希望を伝える権利はあります。
そのため、建築家の先生の人柄や、こちらの意見を取り入れてくれるかどうかは、事前に聞いておいてくださいね。建築家のコミュニケーション能力は営業マンより落ちるケースが多いので、その点は注意が必要です。
まとめ
建築家と建てる家のリスクと盲点8選
- 打ち合わせ回数が少ない
- 性能を軽視する
- メンテナンスを考えない
- 住むと不便な間取り
- 金額が高くなる
- 追加費用の金額を把握していない
- 施工のトラブル
- プライドが高い